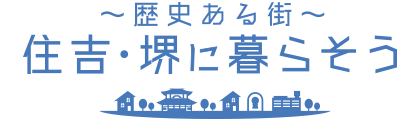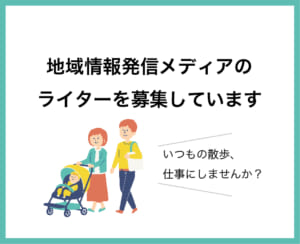南海電鉄の住之江駅を降り少し西に向かって歩いたところ、住宅街のなかに小さな公園があります。その名は霰松原(あられまつばら)公園。
公園と言っても広さは学校の体育館ほどで、遊具が置かれているわけでもなく、訪れる人が多い場所ではありません。
しかし現地を訪れた人にしかわからないインパクトはなかなかのものがありまして……。
神秘的!街中にそびえる2本の巨大クスノキ

ドーーン!といきなり出現する巨木に目を奪われてしまうわけです。
しめなわで飾られている2本の御神木はこの公園を象徴するもので、隣にある小学校の校歌にもうたわれています。樹齢は1000年を超えるとか。
この大樹のおかげで周囲の空気が澄んだものに思えてきます。ずっとこの場所で人々を見守ってきたのでしょうね。
ここは昔○○だった!

写真からもわかるとおり、クスノキはあるのですが、松原らしいところはどこにもありません。というか、公園内に松は1本も生えておりません。
実は昔、この公園のある場所は海岸だったのです。
江戸時代中頃までは風光明美な場所として有名で、公園の前には「岸の辺の道」と呼ばれる紀州街道が通っていました。
当時は白い砂浜と緑の松原がここから堺まで続き、その白と緑のコントラストの美しさは「住吉模様」として今も和服のデザインに残っています。
「小夜更けて 霰松原住よしの うち吹く風に千鳥なくなり」(藤原知家)など、和歌にも詠まれた景勝地でしたが、1704年の大和川の付替工事や新田開発などが盛んになり、遠浅の海は埋め立てられていきました。
現在、海岸はここから8km西にまで遠ざかっています。
ちなみにここの地名は安立といいますが、その由来となった安立という人がこの地にきたとき、松が7本だけ残っていたそうです。
しかし、それはやがて畑になり、七本松という地名だけが残ったという言い伝えがあります。
昔は松がまばらに生える松原を意味する「あらら松原」という言葉があり、それが転じて「あられ松原」→「霰松原」になったようですね。
万葉集の句碑

公園内には石碑が建てられており、万葉集の歌が記されています。
「霰打 安良礼松原 住吉乃 弟日娘与 見礼常不飽香聞(あられの吹き付ける松原を住吉に住む遊女と共に見ているといつまでも飽きない)」とは奈良時代の皇族、長皇子(ながのみこ)が詠んだもの。
706年に父の文武天皇と共に大阪を訪れた際の歌だとされています。
公園内の神社
公園内にはそのほかに、霰松原神社が建っています。

鳥居と社のかわいらしい神社ですが、瀧川稲荷、楠明神、朝日明神、霰松原荒神、金高大明神が祀られていて、金高大明神にはユーモラスなタヌキの像が安置されていました。
かつては天水分豊浦命(あめのみくまりとようらのみこと)神社の跡だったらしく、住吉大社に伝わる「住吉大社神代記」には「天水分豊浦命紳」の記載があるので、往時は住吉大社との関係が深かったようです。
霰松原の由来

この公園の由来について説明する看板が建てられています。
天水分豊浦命神社は荒れていた時代があったらしく、住吉名勝保存会の尽力により昭和52年にこの地一帯が整備され、今の公園にいたっています。
室町時代の公家、三条西実隆の「高野参詣日記」には霰松原がこう書かれています。
「和泉の堺にまかりこゆとて、みちすがらの名のある所どもいひつくすべくもあらぬ見ものなり、霰松原といふ所をすぐとてみれば世のつねの松のはにも似ず、吹からしたるやうにみえ侍れば(大阪の堺に来たが、道中は言葉で言い尽せないほどの名所ばかり、霰松原という所を通ると、そこの松葉は普通の葉ではなく寒風で枯れたようにみえる)」
彼を感動させた松原は既に失われてしまいましたが、こうして往時を偲ぶことが出来る場所が存在することはとてもありがたく感じました。
霰松原(あられまつばら)公園
住所:大阪市住之江区安立2-11
アクセス:南海本線「住之江駅」から徒歩約5分
TEL:06-6691-7200(長居公園事務所)
営業時間:24時間
定休日:なし
駐車場:なし